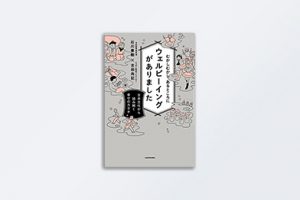心理学とデザイン、というと最近ではセットで語られる場面が多いように感じます。商業デザインの場合、そのデザインを採用するには目的があって、それは大抵の場合「数値の改善」だったりしますよね。ECサイトの売上だったり、ランディングページのCVR改善だったり、広告のCTRアップだったり。それぞれの組織で設定されていると思います。
マーケティング視点ではこれまでのデータの分析を元にすることが多くなりますが、それは「これまでの”過去”の分析の結果」であり、データだけを見ていると目先・小手先の改善になることもしばしば。デザイン的にどうなの…?な案に着地することもあるあるかもしれません。
心理学視点を取り入れることで、目的を見据えた素敵なデザインにまとめつつ、クライアントを説得できる納得感あるプレゼンができるかもしれません。
デザインに活かせる心理学とは
人の心と行動を促すために
心理学とは、ある事象に対する人の心や行動を科学的に研究する学問で、近年特に注目が集まっています。テクノロジーの進化とともにスピードが求められる現代では、精神的に疲れてしまう人の心理の解明や、病気の予防の観点からも様々な研究がなされています。
学問としての研究が進むのと同時に、経済や人間関係の部分でも心理学を活かして求める効果を出すために心理学は取り入れられています。それも当然ですよね。すべての社会活動には人間、つまり「人の心=心理学」が関わってくるのですから。
人に気持ちよく理解と行動を促すことでお互いに良い結果を手にすることができるのであれば、ぜひうまく心理学を取り入れていきたいところです。
基礎心理学と応用心理学
心理学と名のつく言葉はたくさんあり、書店などでもいろいろな「〇〇心理学」の本を見ることができます。
その大元となる心理学は大きく2つに分けることができます。
基礎心理学
全ての人間が持つ心の仕組みを科学的に分析・解明する学問です。
- 生理心理学
- 認知心理学
- 発達心理学
- 学習心理学
- 社会心理学
- 性格心理学
- 行動心理学 など
応用心理学
基礎心理学を踏まえて、更に人間社会の中での活用を目指した学問です。
- 臨床心理学
- 犯罪心理学
- 産業心理学
- 教育心理学
- 家族心理学
- 災害心理学
- スポーツ心理学 など
上記のうち、デザインに活かせる心理学という分類は難しいですが、人の行動のどの段階にアプローチしたいかで考えると良いと思います。
例えば、「うちの商品をもっと知ってほしい」なら認知心理学メイン、「うまく動線を作って購入ボタンまで誘導したい」なら行動心理学メイン、というように。
 かえる
かえるなるほど。
いろいろな心理学があるのはわかったけど、『商業デザイン』で使える知識をまとめて知りたいのよね…
そんな方におすすめするデザインの心理学本がこちら!
[買わせる]の心理学
デザイナーもマーケターも手元に置いておける一冊
目的を持った商業デザインにおいて、どんな心理学がどんな効果をもたらすのかを一つ一つ例を載せて解説しています。
一般的に事業会社で求められるデザインは売上の成果を求められるものがほとんどです。それぞれの実務で「なぜそうするのか」相手を説得する必要がある場合に心理学での裏付けを提示できることは仕事をスムーズに進めることに役立ちそうです。
実務でマーケターとデザイナーに心理学が必要な場面
マーケター
- 分析を元に次の施策を考える必要がある時
- 仮説に納得する根拠が求められる時
- 数字だけを根拠にした改善案に限界がある時
デザイナー
- 依頼主が求めるデザインと上げたい成果に乖離がある時
- 「なんとなく」の好みで変更を希望された時
わかりやすい構成で取り入れやすい工夫
この本の中では、
目的別INDEX
- コーポレートサイトの運用視点
- ECサイトの運用視点
- 広告ランディングページの運用視点
- アプリ開発の運用視点
がまとまっているため、自分の業務に当てはまるものをすぐ探すことができます。
また、それぞれの効果を説明したページでは
- 心理解説
- ダイジェスト
- Webサイトへの応用例
- デザインに活かす三箇条
がすでにまとめられているので、何がポイントなのか、どう活かすことができるのかをすぐ知ることができます。
事業会社ですぐできる!心理学
UIに説得力を持たせるなら
アンダードッグ効果(P.68)
応援してもらうストーリー展開でユーザーの共感を得て、信用アップを狙う。
ツァイガルニック効果(P.90)
未完成なもので気を引き、続きが気になる心理でユーザーを引き込み、商品の良さを伝えるきっかけに。
CVR改善の提案をするなら
フォールス・コンセンサス(P.104)
みんなの「普通」を数字として提示することで、思い込みを覆し受け入れてもらいやすい心理状態を作る。
ザイアンスの法則(P.84)
時間をおかずに頻繁にユーザーと接触(目に触れる)ことで信頼と好感度を上げる。
離脱を阻止する案なら
テンション・リダクション(P86)
購入後に関連商品を進めるなど、気が緩む瞬間に納得感を得られれば合わせ買いで利益アップ
コンコルド効果(P.120)
ポイントなどを設定することで「こんなに集めたのにもったいない」心理を引き出す
プロスペクト理論(P.150)
有効期間など「限定」の設定で利益をあげられるかも!の期待を引き出す
まとめ:じっくり派にもスピーディ派にもおすすめ
じっくり読み込んで知識を自分の引き出しに格納するのもよし、知りたい心理効果をさっと引いて仕事に役立てるのもよし、の『[買わせる]の心理学』。実務でデザイン、マーケティングどちらも携わる私にとっては、手元においていつでも参考にできてアイディアや相手の説得に困った時に大変役立つ本だと感じました。
スッキリシンプルながら白い紙に厚盛ニスの黒を使った表紙と、そこに映える黄色の帯。本書の中の配色も黒・黄色の2色刷りで読みやすくおしゃれな装丁も気に入っています。
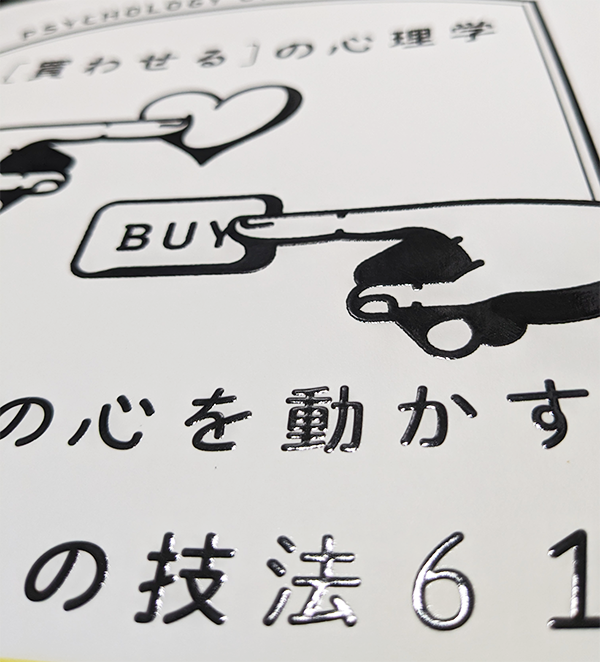
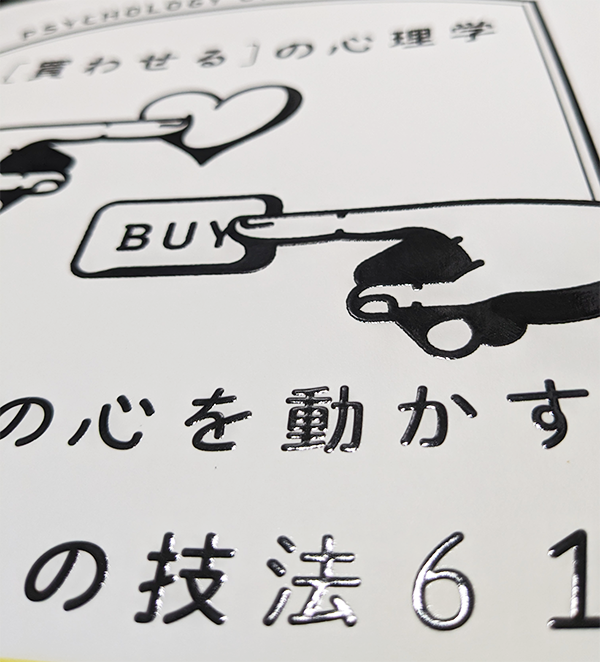
特にECサイトの運営をされている人、アプリ開発のコンバージョンを上げたい人などに有益ではないでしょうか。